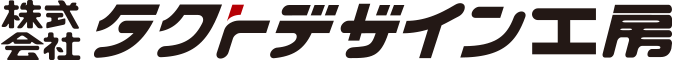雨、降りだした後
こんにちは
大阪支店の武田です。
本日は雨が降り出した後、建物の配管/その他もろもろにそれぞれの動きに着目していきます。
そもそも、建築物は地震や火事など有事の際に向けて法律が整備されています。
その中でも、とりわけ「雨」というのは頻繁に起こる事象です。
・屋根
屋根についてよく見ていると、勾配屋根であれば雨受けがあります。勾配のない屋根(陸屋根)だと雨が溢れてこないように少し立ち上がっています。
イメージしやすいもので言うと、デパートの屋上には手摺の下部分で立ち上がっている箇所があります。
このように、屋根は雨から内部を守るとともに、建物の外に雨が溢れ出ていかないような工夫をしています。
・ルーフドレン
屋根から雨はどこにいくのでしょう。
答えはルーフドレンと言われる配管を伝って排水されます。
建物の外側に配管が付いていると思いますが、あれは大体がルーフドレンです。
・排水桝
ルーフドレンを通った雨は最終的に地中を通り、排水桝へといきます。
大体はマンホールにあり、そこに向かうために雨は1/100というごくわずかな勾配を頼りに伝っていきます。
さて、屋根に降り立った雨のその後を書きましたが、続いては直接地面に降り立った雨のその後を見ていきます。
・水勾配
外構の計画では、地面が水平のようで実はごくわずかな勾配があり、それは雨のための道しるべである水勾配です。
地面に降り立った雨は、配管の勾配と同じく1/100の勾配を頼りに排水溝を目指します。
・グレーチング(排水溝)
水勾配を道しるべに、移動した雨はグレーチングの下の排水溝を通ります。
グレーチングとは、網々状になっている物を落としたら取り出すのに苦労する鉄格子のことです。
この溝も同じく1/100の勾配を頼りに屋根に降り立った雨とともに排水桝へと向かいます。
ここまでが地面に降り出した雨のその後です。実は各マンホール(排水桝)に流すことが出来る雨の量もコントロールされていて、それを超える場合雨水貯留槽というものを設けなければならないということもありますがそれはまた次回のお話で。
以上のように、何度も訪れる雨のために実は建築はかなり頑張っています。
みなさんも雨が降った際には、建物のこと応援してあげてください。
武田